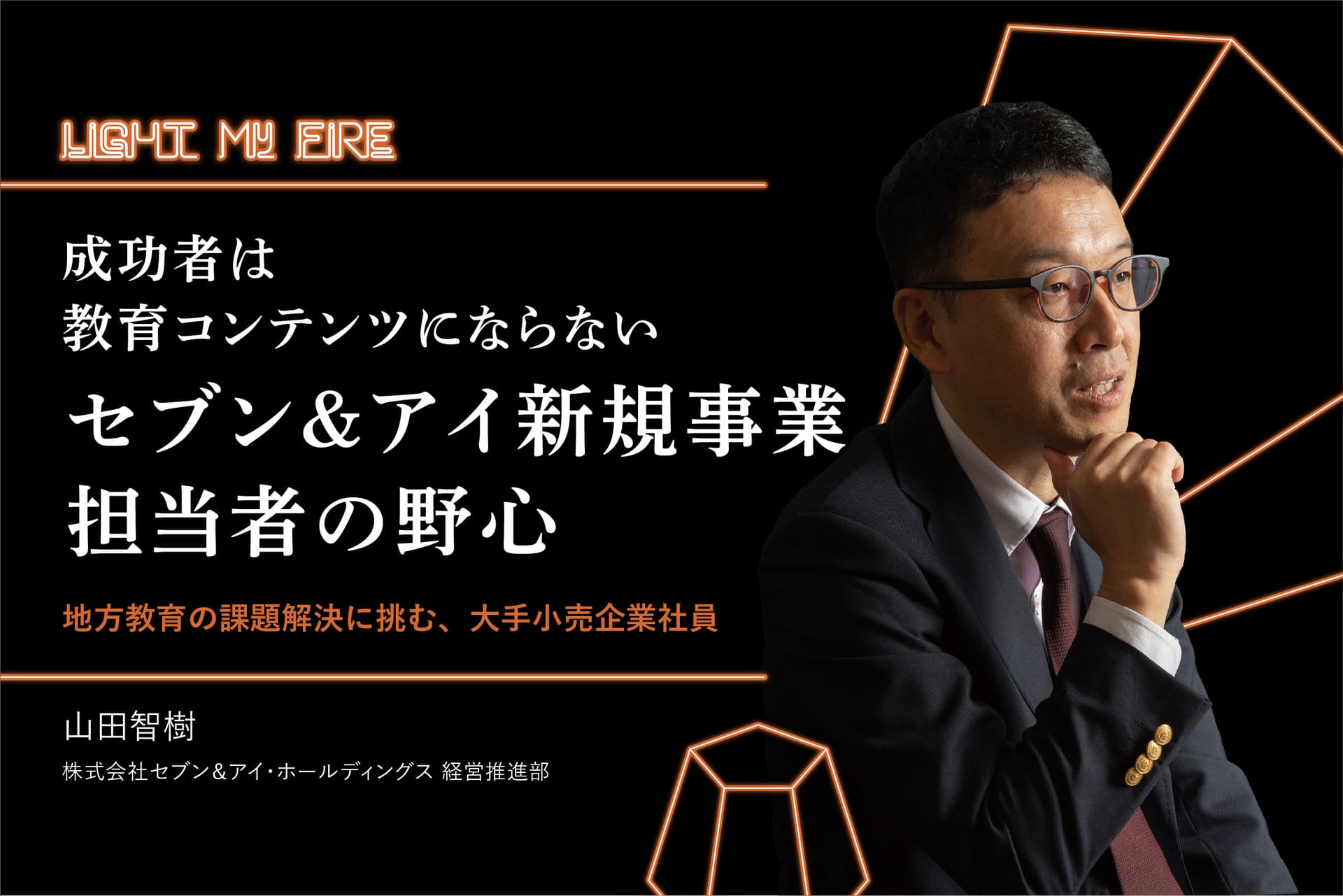
2020年、セブン&アイ・ホールディングスは中学生向けのオンライン教育プラットフォーム「D-Stadium」を開講した。全国の子どもたちが多様な大人の生き方・考え方に触れられる新しい「キャリア教育プログラム」を提供しており、宮崎市の中学校のカリキュラムなどに導入されている。しかし、なぜ流通大手のセブン&アイが「教育」に参入することになったのか? その原点には、新規事業を担当する山田智樹氏による「地方の子どもたちに、多様な生き方・キャリアを伝えたい」というあふれんばかりの熱意があったという。山田氏に事業立ち上げの経緯やモチベーションの火種について伺った。
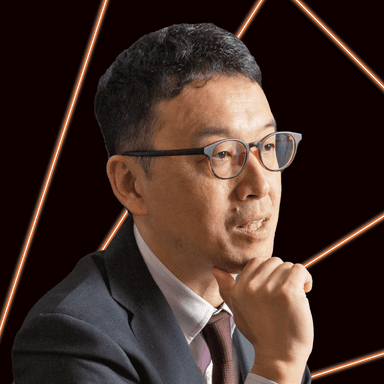
山田智樹
株式会社セブン&アイ・ホールディングス経営推進部
株式会社セブン-イレブン・ジャパンを経て、セブンドリーム・ドットコムでサービス事業の立ち上げ、セブン銀行で新規事業創出に携わる。現在はセブン&アイ・ホールディングスにて、中学生向け教育プログラム「D-Stadium」を主宰。立命館大学客員教授。一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム企画委員。
「決済事業をやっている場合じゃない」
2020年、セブン&アイ・ホールディングスが「教育」に参入したのは、山田氏の「ある地方での体験」が発端だった。
「D-Stadiumを立ち上げる3年前、私はセブン銀行でATMに代わる新規事業を検討していました。当時、キャッシュレス決済が浸透していなかった地方を視察していたのですが、過疎地の学校や子どもたちの現状を知るうちに『地方には、決済より先に解決すべき課題がある。それは教育なんじゃないか』と思うようになったんです」
以前からあった過疎地の学校の生徒不足問題の一方で、コロナ禍で地方移住の流れが加速。山田氏が地方を訪れていた2017年頃からその動きは起こりつつあった。
自分で環境を選択できる大人は良いとしても、子どもたちは自分の環境を選べない。多感な時期に「出会いの選択肢」を制限される子どもたちに対する、こんな懸念が膨らんでいったという。
「豊かな自然のある田舎の暮らしはとても羨ましく思います。その一方で『自分は何者か?』を探している子どもたちには、多様な世界や大人と出会い、将来をイメージすることも大切だと思ったんです。もちろん都市部でも、限られた環境で暮らしている子どもたちがいると思います」
そうした子どもたちに、環境に制限されることなく多様な世界に出会える機会を提供できないかと山田氏は考えた。それが、オンラインによる教育プラットフォーム「D-Stadium」の構想につながったという。
「多様な生き方や考え方をする大人『面白人』と中学生が、オンラインでコミュニケーションする対話型のコンテンツを用意しました。
面白人は、大企業で新事業を手掛ける人、レスリング元日本王者から社会起業家、ものまね芸人、ロボットエンジニアまで様々。自分の生き方を貫いている個性的な大人を集めて子どもたちと対話してもらうことで、子どもたちが自らの将来をイメージするきっかけになればと考えました」
成功者というロールモデルに教育的な価値はない
いわば、新しい形のキャリア教育。しかし、いわゆる「成功者というロールモデル」を伝えることは一切しない。多様な大人の生き方や仕事観、モチベーションに子どもたちが直に触れ、自分との共通点や違いを感じてもらうことに主眼を置いている。
「いま活躍している人がサクセスストーリーを語ったところで、『その仕事、10年後もあるの?』って話じゃないですか。これだけ変化の大きな時代に、過去の成功例を伝えることが本当にキャリア教育なのかと。そのため、大人の参加者には会社名や肩書き、業界用語は一切使わずに自分の人生と仕事を説明してもらっています。子どもたちは我々が思うほど会社のネームバリューには興味がありません。
大事なのは、子どもたちが自分の意志で進む道を決めること。そのために様々な大人へ『何が転機になったか』と質問する機会を届けることだと思います」
さらにD-Stadiumのプログラムは、参加した大人側にも貴重な学びの機会を提供しているそうだ。
「大人側は、会社名や肩書きを使わずに自己紹介するために、自分の人生や仕事の本質を捉え、シンプルな言葉にする必要があります。
その本質的な自己開示に対して、子どもたちから率直な反応やフィードバックが得られるわけです。じつは、これが参加する大人たちからも、自己を振り返り、再発見し、アンラーニングする機会になったと評判なんです。D-Stadiumは子どもたちだけでなく、大人にとっても十分に価値のあるコンテンツになると確信しましたね」
会社の域を超え、自身のライフワークに
この反応をふまえ、D-Stadiumの事業設計を練り直した山田氏。現在は、社会人向けアンラーニングプログラムとしてマネタイズし、子どもたちに「多様な世界や生き方に出会える」機会を提供する、一石二鳥のビジネスモデルへと舵を切っている。
「会社の新規事業なので、今後、継続を断念する可能性もあるでしょう。でも、仮にそうなったとしても何らかの形で継続できる道を模索するつもりです」
子どもたちの現状に対して強烈な当事者意識を持ち、事業に邁進する山田氏。その胸の奥では、どのような「モチベーションの火」がともっているのだろうか。
「とくに自分の生い立ちが同じだったわけではないのですが、やはり地方の子どもたち、とりわけ過疎地域に暮らす子どもの実情を知ってしまった以上、そう簡単に投げ出すことはできません。子どもたちからお願いされたわけではなく、もしかしたら余計なお世話かもしれません。
でも、参加した子どもたちが、誰にも言えない内心を告白したり、「自分は何者か」に気付くシーンを何度も目撃しています。子どもたちが住む場所や環境に左右されず、なるべく多くの機会を得ることには大きな意義があるはず。そう信じて、これからも挑戦していきたいですね」
【私の着火法】
新規事業の視察中に、過疎地の学校や子どもたちの現状を知ってしまったこと。それがすべてです。
(2023年1月20日発売の『Ambitions Vol.02』より転載)
text by Noriyuki Enami / photograph by Takuya Sogawa / edit by Kohei Sasaki
