
2025年10月、ローカルで活躍するリーダーたちが一堂に会し、九州の未来を描く「ONE KYUSHUサミット」が開催された。 2020年のオンライン開催から4回目となる本イベント。毎回九州内で開催地を変更してきたが、初めて長崎県五島という「離島」での開催となった。 九州の中心地ではなく、離島から、同じくひとつの島といえる九州を見つめるという今回の企画。五島市図書館の会場には130名を超える観客が、五島、九州、そして全国から集まった。 複数のセッションから、ポイントを振り返る。
OPENING SESSION 九州の勝ち筋の探求
出口太氏(五島市長)の挨拶や地元の高校生によるプレゼンテーションなど賑やかな幕開けとなったオープニング。
会長・村岡浩司氏、実行委員長・髙田理世氏、大筋暢洋氏(経済産業省 九州経済産業局)が「九州の勝ち筋の探求」について語り、この日行われる議論の方向を示した。

日本の一割経済と呼ばれることの多い九州経済。特徴的なのは、一次産業から製造、サービスまで多様に広がる地域ごとの特性にある。
これまでは、域内総生産(GRP)向上のために選択と集中の競争が求められてきたが、昨今は柔軟性や多様性、包摂性に注目が集まり始めており、多様性を誇るひとつの九州としての魅力が向上している。
その魅力を高めるためにも、人口が減少する中、いかに九州内での人や仕事の流動性を高めていくかが重要だ。


SESSION.01 九州の離島経済と、その挑戦が描くつながりのかたち

「離島経済」をテーマに、鹿児島県 甑島で複数の事業を展開する山下賢太氏、東京の建設会社から五島にIターンし、島内有数の宿泊業・カラリトを運営する平﨑雄也氏、「窓」というプロダクトで遠隔地をつなぐ阪井祐介氏らが議論。
マクロ経済の文脈では「弱者」として扱われる離島経済。その実態の分析から、都会の資本経済だけではない、離島特有の社会資本の存在について存分に語った。
※該当セッションの詳細は別途レポートします。
SESSION.02 九州のこれからに必要なローカルゼブラ的ビジネスとは?

「ローカルゼブラ」とは、急成長を遂げるスタートアップを指す「ユニコーン」に対応する言葉で、社会性と経済性の両立を目指すスタートアップを意味する。
セッションではスタートアップ、メガベンチャー、そして大企業という異なる立場の登壇者が、それぞれが取り組む「社会性と経済性の両立」について語った。
2025年時点、この問いに対する明確な正解は存在しない。
そんな中、西部ガスの小川周太郎氏が発言した「大企業を使う」という視点は特徴的だった。
大企業の事業ポートフォリオの中で、社会善につながる活動を「事業貢献に資するひとつの取り組み」として組み込むことで、個人やスタートアップでは困難な活動も実現する。ひとつの攻略法として提示した。

SESSION.03 世界がひらく、九州の関係経済
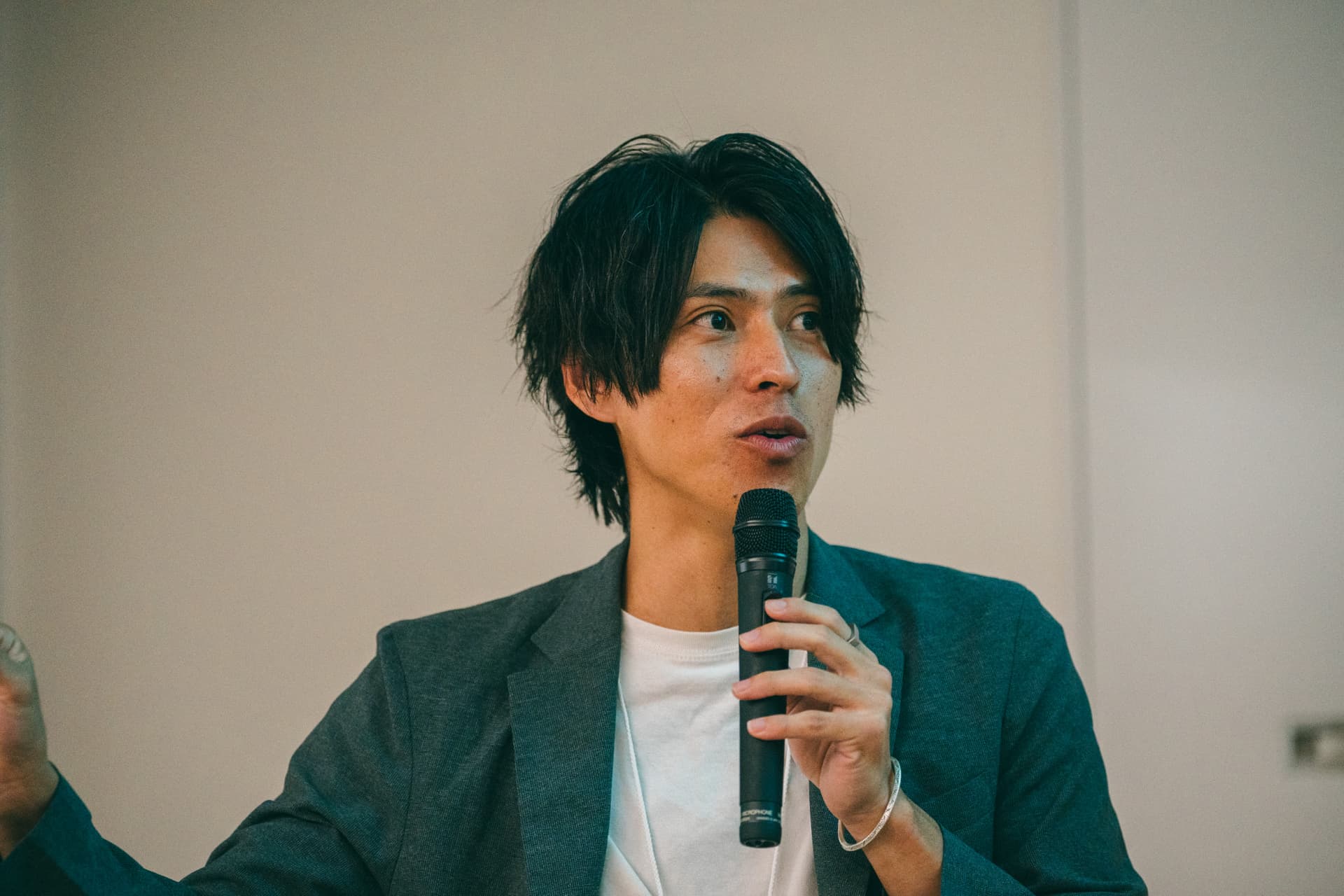
昨今、インバウンドにより賑わいを取り戻している九州経済。
本セッションの中心は、登壇者である小吹智広氏(NomadResort)、大瀬良亮氏(遊行)の2名が携わる「デジタルノマド」だ。一般的な観光ではなく、一定期間暮らしながら働く人々(デジタルノマドワーカー)の間で、福岡、長崎に注目が注がれている。
デジタルノマドの場合、従来の刊行よりも、よりオーセンティックなジャパンを感じたいというニーズがある。従来の東京〜大阪を中心とするゴールデンルートではなく、あえて離れており、日本の原風景が残っている九州が選ばれているという。
また、2024年のONE KYUSHUでは、「九州という名称は世界地図になく、世界に認知されていない」という議論が起きたが、今回は逆。一部のニーズ調査によると、福岡・長崎ではなく「九州」というエリアとして求められたという結果が出たという。
世界から見た「九州」の見え方が大きく変わる、まさにそのタイミングにあることが見えた。

SESSION.04 地域の可能性を見つけ、育て、広げる共創の力
離島の可能性に魅せられて「移住」した2名(池田武司氏・パーソルキャリア)、門田クニヒコ氏(五島つばき蒸留所)の体験を中心に意見交換が進んだ。
長年、キリンでマーケティングを行ってきた門田氏は、五島の特産品である椿を活用したクラフトジン「GOTO GIN」を製造・販売している。

離島で新しい事業を行う上でハードルとなることのひとつに「地域の人々に求められていないものは受け入れられない」ことがある。
門田氏は、五島の産業である椿を使う、同じエリアにある教会の保全管理を自ら行うなど、土地の人々が大切にする文化の上で、大量生産とは異なるジンづくりを実現している。
また、セッション3、4ともに、台湾と九州をつなぐプレーヤーが登壇していたことも今回の特徴だった。九州は日本の中でもアジアに近い。一つの経済圏の可能性を語ることも重要だが、アクセスがよく数時間で行き来することができるアジアとの連携が、これから一層進んでいくと予想される。

前夜祭・本番・翌日のフィールドワークと、全3日間開催されたONE KYUSHUサミット。
20代以下という若いチームにより運営が行われており、「九州の未来を議論する」という主体の世代交代が鮮明に打ち出されたのが印象だった。

また、セッションはそれ以外に印象深い点をあげるとすると、島で過ごした余白の時間だ。
島からの帰路の途中、「島の人はみんな好きなんですよ」と案内いただいた「鬼岳(おんだけ)」から見下ろした五島市の景色や、集落を歩いて見た光景、道路の草の生え具合などから感じる人々の暮らしの温度、養鶏所の近くの強烈な臭いなどが、記憶に強く残っている。
どこにいても世界中の公開情報にアクセスできる今。手軽な情報でわかったふりをすることは簡単な時代だ。
一方、離島のように、都会に比べて情報量が少なく、インターネットやAIでは解像度高くアクセスできない世界は、膨大に存在している。しかしデジタルではなく、五感をもって獲得するまで、その存在に気づくことは難しい。
五島は企業のフィールドワークなどが行われる場所でもあるというが、ビジネスパーソンが、遠方に「わざわざ行き、学ぶ」理由はそこにある。机上にいては見えない言語化できない存在に気づくこと、固定された視座がリセットされることに、体験の価値があるのではないだろうか。

photographs by Daichi Mochida
