
事業環境が目まぐるしく変化する昨今、地域の中核企業も新規事業開発やオープンイノベーションの取り組みは避けて通れない。 創立20周年を迎えた西日本シティ銀行では、地域の中堅・中核企業の「新規事業開発」「オープンイノベーション」のビジネス実践知を学ぶイベントとして、『FUKUOKA INNOVATION DAY〜イノベーターに学ぶビジネス開発の成功法則〜』を開催。 本記事では、インターネットを使ったさまざまなサービスを立ち上げ、幾度となく成功を収めてきた連続起業家の家入一真氏が「ビジネス創出に必要な視点」について語った基調講演の内容をお届けする。
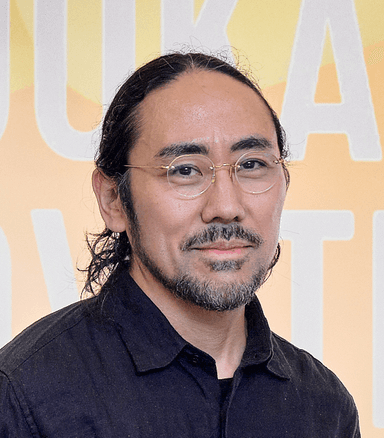
家入一真
起業家/株式会社CAMPFIRE ファウンダー会長
2003年株式会社paperboy&co.(現GMO ペパボ)創業、2008 年JASDAQ 市場最年少(当時)で上場。2011年株式会社CAMPFIRE創業。2012年BASE株式会社を共同創業、東証マザーズ(当時)上場。2018年ベンチャーキャピタル「NOW」創業。京都芸術大学客員教授やN 高起業部の顧問等を務める。
「居場所」に救われた体験が、起業家の原点
僕は中学時代にいじめを経験して、不登校になりました。孤独な日々の中でインターネットと出合い、そこで初めて「居場所」を見つけたんですね。見知らぬ人とつながって自分の表現を発信できる喜びを感じ、本当に救われた。この経験がその後の僕の人生、そして起業家としての活動の原点になりました。
20代前半で立ち上げた「paperboy&co.(現・GMOペパボ株式会社)」は、個人がホームページやネットショップを簡単に作成できるサービスです。当時、インターネットはまだ一部の人々のツールでしたが、僕は誰もが気軽に情報発信や経済活動を始められるようにしたいと考えていたんです。

「誰もが自由に表現し、つながり、小さな経済活動を始められるように」。
このビジョンを実現するために、レンタルサーバー「ロリポップ!」やハンドメイドマーケット「minne」など、個人をエンパワーメントするサービスを次々と展開していきました。
後に同社はGMOインターネットグループにジョインして、JASDAQ市場に上場を果たします。「paperboy&co.」での経験は、僕に大きな自信と、社会を変える力を持つインターネットの可能性を確信させてくれました。
その後も、クラウドファンディング「CAMPFIRE」、ネットショップ作成サービス「BASE」などを立ち上げました。これらの事業は一見バラバラに見えるかもしれませんが、「居場所をつくる」「誰もが声を上げられる世界をつくる」という共通のビジョンで貫いています。
僕にとって起業とは単なるビジネスではなく、社会貢献活動でもあるのです。
新規事業を創出し、成功に導くポイント
これだけ連続で起業していると、「新規事業のアイデアはどこから生まれてくるのか」とよく聞かれます。僕の場合は、流行を追うのではなく、自分の原体験と社会課題を結びつけることから始まるのがほとんどなんですね。
全く新しいアイデアを思いつく必要はなくて、足元に転がっている小さな石ころを拾い、磨き上げるように、身近な課題や見過ごされてきたニーズに目を向ける。

たとえば、「CAMPFIRE」は、震災復興の支援という社会課題と、個人が資金調達できる仕組みを作りたいという思いが結びついて生まれたサービスです。当時、日本でクラウドファンディングの概念は一般的ではありませんでしたが、震災をきっかけに多くの人が支援の必要性を感じていました。
僕は、この社会的なニーズを捉え、クラウドファンディングという新しい仕組みを日本に広めることに成功しました。ユーザーにとって本当に必要なものは何かを追求し続けるのが大切なのだと思います。
とはいえ、新規事業は計画通りにいかないことの方が多く、成功までの道のりは本当に険しいものです。だから、起業家の「心」のケアはすごく重要だと思うんですね。
僕自身、「paperboy&co.」の上場後、精神的に疲弊して会社を去ることになりました。この経験から、起業家のメンタルヘルスの重要性を痛感し、起業家支援プログラムの中でメンタルヘルスケアを提供しています。うまくいかないときこそ、なぜこの事業を始めたのかという「原点」に立ち返ることが大切です。そのためにも、起業家の心のケアには積極的に取り組んでいます。
加えて、既存事業とのバランスを取ることも大切で、僕は「両利きの経営」という考え方を重視しています。
既存事業を深掘りしつつ、新しい事業にも挑戦していく。既存事業で培ったノウハウやリソースを生かしながら新しい市場を開拓し、ユーザーの声に耳を傾けながら執念を持ってプロダクトを磨き続けていく。これが持続的な成長につながると信じています。
大企業における新規事業の課題と解決策
大企業が新規事業を生み出すことの難しさは、よく分かります。スピード感の欠如、保守的な社内文化、心理的安全性の低さなどが、新規事業の芽を摘んでしまうことはよくある話です。

大企業には社会的に影響力の大きい既存事業を守る使命があるから、リスクを伴う新規事業への挑戦に慎重になるのは当然のことでしょう。しかし変化の激しい現代において、イノベーションを起こし続けることは、企業が存続できるかどうかに直結する、重要な取り組みです。
大企業が新規事業を成功させるために必要なのは、トップのコミットメントと、長期的なビジョンです。トップが率先して新規事業の意義を語り、社内全体を巻き込んでいく。一方で、トップダウンだけでなく、ボトムアップで新規事業を推進することも大切で、社員の自発的なアイデアを尊重することで、より革新的な事業が生まれる可能性が高まります。
また、既存事業との軋轢を避けるために、社内ベンチャー制度などを活用して、独立した組織として運営することも有効な手段です。既存の組織とは異なるルールや評価基準を設けることで、新規事業の成長を促進できるでしょう。
そして何より重要なのは、挑戦する文化を醸成することです。失敗を恐れず、新しいことに挑戦する姿勢を評価することで、社員のモチベーションを高め、イノベーションの促進につなげていく。大企業がスタートアップのようなスピード感と柔軟性を持つためには、組織文化の変革が必要だと考えています。

人口減少社会におけるスタートアップの役割
すべての事業は、「一人」の情熱から始まります。これは「ソース原理」と呼ばれる考え方で、僕自身も強い思いを持って事業に取り組んできました。なぜこの事業に取り組むのか、どんな未来を目指しているのかを明確に示すことで、共感してくれる仲間は集まってきます。
僕の場合は、「居場所をつくる」「誰もが声を上げられる世界をつくる」というビジョンに共感した多くの人が、僕の事業を支えてくれて、共に成長を続けています。
では、人口減少社会という大きな課題に直面している現在、我々はこの課題にどう向き合って貢献すべきでしょうか。僕は人口減少をネガティブに捉えておらず、新しい社会のあり方を模索するチャンスだと考えています。
たとえば、テクノロジーを活用することで、生産性向上や生活の質の向上、人手不足の解消、高齢化社会における医療や介護の課題解決など、スタートアップが貢献できる余地は大きく、スタートアップの役割がますます重要になると思います。
僕の経験から言えることは、自分の原体験と社会課題を結びつけて、情熱を持って事業に取り組むことが大切だということ。どんな小さなことでも、情熱を注ぎ込めば大きな力になります。そして、それは必ず社会を変える力になるでしょう。

最後に、僕の故郷である福岡は、スタートアップ都市として成長を続けています。行政の支援、活発なコミュニティ、優秀なエンジニアなど、多くの魅力がありますよね。地方での起業は、東京に比べて不利だと考えられがちですが、福岡はその常識を覆しつつあります。
僕自身も、福岡のスタートアップコミュニティに積極的に関わって、若者の起業を支援していますし、福岡を「スタートアップの聖地」にする夢の実現に向けて尽力しています。同時に、僕自身のビジョンのもと、新しい事業開発に情熱を注ぎ続け、社会に貢献できれば嬉しいです。
text by Tomomi Tamura / photographs by Kensuke Takehara / edit by Keita Okubo
