
技術革新や消費者ニーズの変化で市場が衰退し、本業が揺らいでいる企業が少なくない。 新規事業を足がかりに本業を転換させて生き抜くのか、それともジリジリと追い込まれてしまうのか 。『本業転換』(KADOKAWA/著:山田英夫・手嶋友希)の共著がある早稲田大学ビジネススクールの山田英夫教授に、様々な企業の実例から、成功へと導く作法を聞いた。
富士フイルムが本業転換に成功した理由
本業転換の成功事例の中でも、写真フィルムからデジタルカメラや化粧品、医薬品などへ、多角的な事業転換を成し遂げた富士フイルムホールディングス(以下、富士フイルム)のエピソードは印象的です。
富士フイルムは1934年、大日本セルロイド(現在のダイセル)から写真フィルム事業を独立させる形で創業した会社です。フィルムの需要がまだ伸びている1980年代、デジタルカメラが銀塩フィルムとカニバリゼーションを起こすリスクを知った上で、「他社にやられるくらいなら、自社でやる」とデジタルカメラの開発に着手、1988年には、本格的なデジタルカメラを発売しました。本業であるフィルムの需要が減少する前に手を打ったことが、本業転換がうまくいった1つ目のポイントです。
2つ目のポイントは、本業転換を決断した当時、富士フイルムは国内のフィルム市場で圧倒的なシェアを誇っており、潤沢なキャッシュフローがありました。投資を伴う新規事業を立ち上げる上で、資金面での余力があることは大きな強みになります。
3つ目のポイントは、本業と技術的な関連性の高い事業に投資したことです。2007年、富士フイルムは基礎化粧品「アスタリフト」を発売して話題になりました。フィルムと化粧品は、一見関連がないように感じられるかもしれませんが、写真プリントの色あせを防ぐ抗酸化技術や、写真の光を解析しコントロールする技術は、化粧品の分野にも応用することができるのです。この「技術関連の多角化」も、富士フイルムが本業転換に成功した大きな要因のひとつだと思います。
本業転換を成功させる6つのポイント
1. 本業転換の必要がない時期から、新規事業を始める
「遅れた意思決定は、誤った意思決定よりなお悪い」という言葉があります。本業の売上が落ち、新規事業への転換を決断すべきタイミングがあったとして、2回、3回と現状を変えずに見送り続けると、会社が倒産してしまうかもしれません。本業が衰退し資金が枯渇してしまってからではなく、本業が順調で長期の大型投資に耐えられる資金と体力が残っている段階が、本業転換を始める上でベストなタイミングなのです。
事例1 大塚製薬(大塚ホールディングス)
もともと点滴用の輸液を作る会社でした。市場でも圧倒的なシェアを誇り、キャッシュフローも安定していたのです。その間にカロリーメイト や「飲む点滴液」 とも呼ばれるポカリスエットを時間をかけて開発し、看板事業に育てました。
2. 組織の柔軟性が保たれている
長く本業を守ってきた大企業では、創業から時間が経つにつれ、起業を経験した役員が減っていき起業マインドやスキルが失われがちです。本業が衰退してきたという話題を社内で口にすると、「縁起でもないことを言うな」と聞き入れてもらえない場合もあります。こうして「守り」の風土が強くなり、硬直化した組織では、売上が減少したときにも「一時的なものだ」「今をしのげばまた上向きになる」と考え、転換のタイミングを逃してしまうでしょう 。本業転換には組織の柔軟性が欠かせません。
3. 潤沢なキャッシュフローを確保する
新規事業に5年、10年スパンの投資を行う、あるいは時間をかけて研究開発を行う資金が十分に残っていることが重要です。 本業が衰退し、十分なキャッシュフローが得られなくなってから事業の多角化を進めようとしても、その体力が残っていません。そのため1〜2年で事業化が見込めそうなものに手を出すことになりますが、長期的な視点で将来性のある新規事業に多額の投資をすることが難しくなってしまうのです。
4. カニバリゼーションを恐れずに事業を選択する
本業が順調な時期に本業とのカニバリゼーションのリスクを取ることは「自爆行為」のようにも感じられ、ボトムアップ型の大企業では決断が難しいかもしれません。しかし、これを恐れずに新たな事業を選択することをトップが強いメッセージとして打ち出し、社員が一丸となって取り組むことができれば、本業転換に成功する可能性が高まるでしょう。逆に言えば、本業とのカニバリゼーションを極端に嫌う会社は、うまくいかない場合も多いのです。
事例2 リクルートホールディングス/アマゾン
紙の情報誌を販売していたリクルートは紙での発行に固執せず、ウェブ事業に進出して成 功しています。オンライン書店が祖業のアマゾンはマーケットプレイスや電子書籍に進出す る時に、社内のカニバリゼーションを避けるどころか「推奨」し、新たな事業を推進しました。
5. 本業と新規事業のシナジーを測る
事業選択の際には、本業とのシナジー、つまり相乗効果を測ることも重要です。本業と新規事業の掛け合わせにより、1+1=2よりも大きな成果を得られるかということですね。シナジーとは、本来「何となく本業に近いような気がする」という感覚や雰囲気ではなく、数値で測れるものです。客観的な裏づけを持って事業選択をすることが肝要です。
6. 流通チャネルの協力を得る
本業転換を成功させるには、流通チャネルの協力を得ることも重要です。チャネルとはお客様を集め販売するための流通経路のことで、化粧品の例で言えば、小売業者、訪問販売業者、ECサイトなど、様々なチャネルが存在します。
チャネルとの関係構築においては、上から目線で教育するのではなく、新しい商品やサービスを扱うことでチャネルにどのようなメリットがあるのかを伝え、着実に具現化していくことが大切です。チャネルヘの配慮や目配りができているか、一体となって事業に取り組める体制になっているかも、本業転換の成否を分けるポイントのひとつでしょう。
本業転換への挑戦。経営者が持つべき戦略の4本柱
これから本業転換を行おうとする企業の経営層は、どのような視点を持って体制を整えていけばいいのだろうか 。
1. 若手が経営層へ直接提言する機会を作る
ある会社では、毎年、若手社員を集めてチームを作り、「どうすれば自社を倒すことができるか」を半年ほどかけて検討、提言するプロジェクトを行っています。事業部長や課長ではなく、社長に直接提言をする仕組みで、忖度する必要もなく、本音が言えると聞いています。若手社員だからこそ、古参の役員とは違う、新鮮な視点を持てることもあるでしょう。同様の取り組みを行っている会社を2社知っていますが、どちらも倒産していないばかりか、1社は業界のトップを走り続けています。社内の風通しの良さを実現する上で、有効な施策ではないでしょうか 。
2. 「新規事業は一日にして成らず」と心得る
大企業の中には、社内に新規事業の芽や提案があっても、百億円、千億円規模の売上が見込めなければ事業とは言えないとして、却下する企業もあります。伝統ある大企業ほど、会社の事業規模を維持することに意識が向いて、最初から本業に匹敵する規模の事業を求めてしまうのです。しかし、始めたばかりの事業が、いきなり数千億円の売上を上げられるはずはありません。「本業に代わるような新規事業は一日にして成らず 」と心得るべきでしょう。
事例3 トヨタ自動車
当初は豊田自動織機製作所という機織り機を作る会社の新規事業としてスタートしました。数十年の歳月を経て、新規事業の自動車が本業をはるかにしのぐ稼ぎ頭に成長したのです。
3. 強みに集中して、「やらないこと」を決める
環境が激変している時期に、未来を予測し、今後何をするべきかを決断することは簡単ではありません。しかし、「何をやらないか」は企業の意志で決めることができます。「やらない」決断は逃げではなく、事業の一貫性や企業理念との整合性を保ち、自社が強みを持つ分野に資源を集中する効果を生む場合があります。
事例4 日清紡ホールディングス
高級な綿糸の生産を行う紡績会社として、1907年に設立されました。戦中、戦後と数十年単位の時間をかけ、エレクトロニクスやブレーキなどの分野へと本業転換を成功させています。ライバル企業が生産効率のいい合成繊維事業に参入する中、日清紡は1950年代に原材料のコストを検討して「合成繊維への進出はしない」と決断しました。合成繊維は石油化学をもとにしているため、1970年代のオイルショックでは多くの繊維メーカーが大きな影響を受けましたが、日清紡は結果的に大きなダメージを免れました。
4. 自社ですべて抱え込まない
現代では事業選択のみならず、経営資源や業務についても「持たない」「やらない」決断が求められるようになっています。高度成長期の日本では、あらゆる産業が成長の途上にあり、大企業に経営資源が集中していました。例えばメーカーなら、研究開発から製造、販売、アフターサービスまでを一気通貫で自社で行っていたのです。そのため、事業を多角化する際にも、自社がどんな資源を持っているかが重要視されまし た。この状態を「バンドリング」と言います。
最近は、自社ですべての業務や資源を抱え込むのではなく、必要に応じて外注したり、他社と共同で行ったりすることが一般的になっています。物流や製造、販売、マーケティングなどを含むバリューチェーンがバラバラになる「アンバンドリング」が進んでいるのです。デジタルトランスフォーメーション(DX)も、アンバンドリングの傾向に拍車をかけています。本業転換を行う場合にも、新規事業に必要な資源をすべて自社でまかなおうとすることは、もはや現実的ではありません。どの部分を自社で行い、どの部分は持たないのか、取捨選択をすることが必要です。
また、「◯◯業界」という企業のカテゴリーによる分類も、過去のものになりつつあります。少し前の例で言うと、リクルートホールディングスやぴあ、楽天グループが創業したとき、彼らはどの業界に属する企業だったでしょうか。既存業界の枠にとらわれないアイデアが、新規事業につながるのではないでしょうか。
(2023年1月20日発売の『Ambitions Vol.02』より転載)
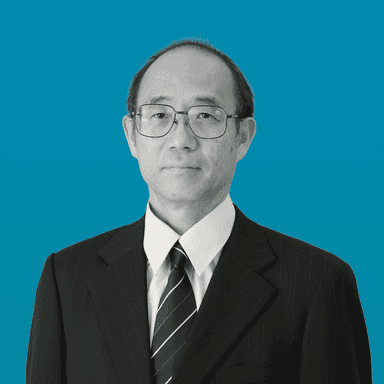
山田英夫
早稲田大学大学院経営管理研究科(早稲田大学ビジネススクール)教授
慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。三菱総合研究所にて大企業の新規事業開発のコンサルティングに従事し、1989年早稲田大学に転じ現職。専門は、競争戦略論、ビジネスモデル。博士(学術、 早稲田大学)。ふくおかフィナンシャルグループ、 サントリーホールディングスの社外監査役。『異業種に学ぶビジネスモデル』『競争しない競争戦略』『ビジネス版 悪魔の辞典』(以上すべて日本経済新聞出版)など著書多数。
text by Mihoko Takahashi / edit by Hidefumi Nogami, Miho Matsuura
