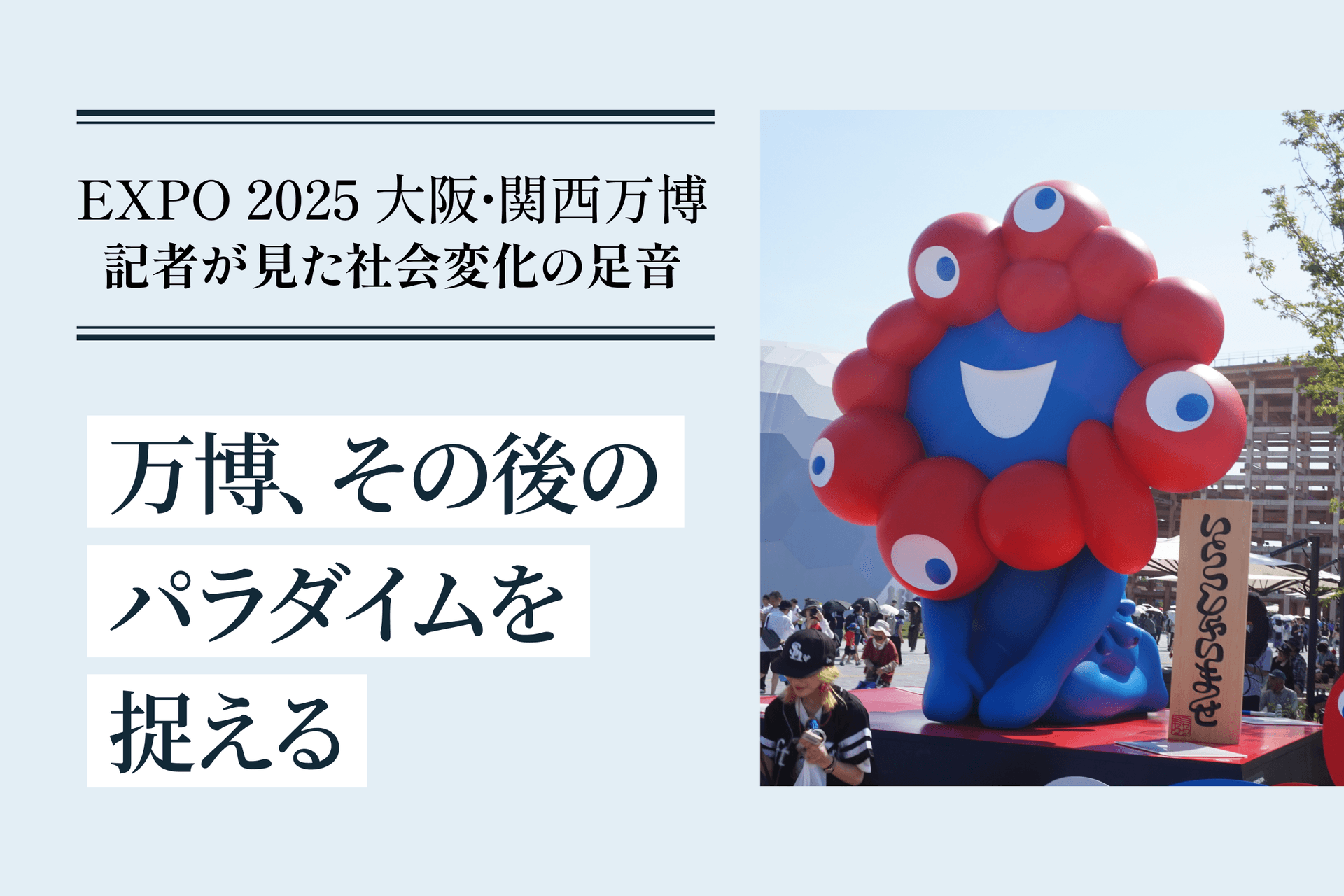
2025年4月13日から10月13日まで開催されている「EXPO 2025 大阪・関西万博」。大阪湾に建設された約390haの広大な人工島・夢洲に、世界から158の国・地域のパビリオンが集まる。目標入場数は2820万人という一大プロジェクトだ。 歴史を振り返ると、「万博」は産業革命に呼応するように誕生し、工業化社会を象徴する役割を担ってきた。つまり「リアル」の時代に生まれ、最適化したひとつのフォーマットといえる。 2025年、「オンライン」で世界中にアクセスでき、価値観が多様化し、同時に分断も進む今。リアルな空間を使う万博とは、社会にどのような影響を与えるのか。 本記事では、万博の現地取材を通したレポートを届ける。 夏休み企画として、万博を楽しむひとつの視点として見ていただきたい。

万博を歩き、まず感じたのはその規模。会場の広さは約155ヘクタールと、東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンの約3倍。
一周2kmある木造建築「大屋根リング」の中に、海外パビリオンと企画性の高いシグネチャーパビリオンが、リングの外に日本や日本企業のパビリオンが集まる。
開幕後、好意的な感想がメディアを踊り、SNSに流れる。世の中の空気の通り、趣向を凝らしたパビリオンは、その外観を見て歩くだけでも気分が高まる。巨大な国際文化祭であり、約半年間の野外フェスティバルだ。

一方、1時間程度の行列を経て入った海外パビリオンのメインは、ややフォーマット化された自国のプロモーションムービーがほとんど。世界的なビジネスイベントが隆盛を極める時代だ。「先端技術」「未来」といった発見は、期待ほどは得られない。

情報化の時代、「新しい情報を得る場所」という万博の役割は終えている。
それでも、約7,600億円とされる費用をかけ、世界中の国々が出展し、連日15万人が集まる、万博というフォーマットの価値は、どこにあるだろうか。
今の時代の万博の役割は「新しい規範に向けて、社会をアップデートする」ことにあるのではないだろか。
パラダイムシフトのドライバーとなる
万博の会場内は、バリアフリーが徹底している。段差がなく、大屋根リングにはエレベーターも完備。実際、会場では車椅子の来場者も多く見られた。
また、会場内ではリサイクルのためのゴミ分別が厳格化されており、その区分はペットボトル、キャップ、缶・びん、紙類など10区分。それを、参加者は当然のように行っているのが印象的だった。
現在、リサイクルの必要性は、おそらく誰もが知っている。
しかし、ハロウィンや花火大会など、不特定多数の人が集まるイベントには、その後の目を覆いたくなるようなゴミの山がついて回る。
それはつまり、ゴミ分別の大切さを知っているものの、行動として実装されていないということを現している。
万博という非日常の空間で、述べ28,000万もの人々が、厳格な分別を当然な行為として「体験」する。これは、ゴミや持続可能という規範が大きく変わる機会になりうる。

若い世代はより顕著だ。
大阪府内の小・中・高等学校等を招待する取り組みが行われており、連日学校単位で参加している。修学旅行などの体験は、その後の価値観を形成する原体験として、記憶と行動に強く残る。彼らが経験した持続可能な取り組みの水準が、以降の当たり前になる。
社会規範の更新は、一朝一夕ではできない。最も早いのは世代交代だ。
次世代の大幅な価値観の刷新に、万博という集団体験が貢献する点は大きいだろう。
「日傘男子」の消滅。社会の「当たり前化」が加速する
次は、少し具体的な足元の気づきだ。
博報堂ケトルファウンダー・嶋浩一郎氏の著書「あたりまえのつくり方」に、新しい行動様式が世の中の当たり前になっていくための補助線として「社会記号」の発生があるという。
例えば「イクメン」のように、男性の育児参加を象徴する記号が生まれることで、多くのステークホルダーがポジティブに捉え、当たり前になっていく。(そして、イクメンという言葉は社会に定着し、社会記号すら消滅している。わざわざ喧伝することがむしろマイナスという)
会場でよく目にした光景が、男性の日傘使用だ。調査によると「日傘をすでに使用している」男性は17.8%。2年前の8.0%と比べ9.8ポイント増加している。わずか2年で倍増しているものの、ようやく加速度的に普及する、直前のフェーズだろう。

万博のパビリオンの行列は、1時間以上になることも多い。
「暑さに耐えられない」というシンプルな問題に対して、多くの男性が日傘で防御している。前段落のゴミ分別にも言えることだが、実際に「新たな行動をとる」という経験をすることで、その価値を体験し、以降当たり前になっていく。

PR・広告宣伝の世界で議論される「社会の当たり前化のプロセス」が、万博という加速装置により一気に進んでいることを目の当たりにした。

※【男性日傘に関するアンケート調査】(10~40代の男性600名対象)
「スイスでもいこうか」フィルターバブルの処方箋
「暑いね」「アイス食べたい、アイスどこに売ってるかな」「スイスとか、あるんじゃない」「じゃ、スイスでも行こうか」
会場内のベンチで休憩していた2名は、そう話してスイスパビリオンへ向かっていった。
※一部パビリオンではその国のフードメニューの提供も行っている。
「次どこ行こうか」「ここ、まっすぐ進んだらオランダがある」「じゃ、オランダのぞいてみようか」
予約が不要な海外パビリオンが密集する大屋根リング内部では、このような「目的外」の出会いが多発する。
アメリカ、フランスなど、日本にとって馴染みの深いパビリオンが人気なのはもちろんだが、アンゴラ、ノルディック・サークル(北欧5カ国共同)、モザンピークなど、あまり日本で情報に接することの少ない国や地域のパビリオンにも人だかりができていた。

インターネットで世界中の情報にアクセスできる時代に、わざわざリアルな場所に出展する、その場に参加する。その価値のひとつは、このような意図せぬ出会いにあるのではないだろうか。
目的に応じた正解が生成される今だからこそ、目的と高精度アルゴリズムの枠外にある情報に触れることは、単純に新鮮で楽しいものだ。
フィルターバブル、エコーチェンバーが叫ばれ、分断化が進む世の中、フィジカルで得るセレンディピティは、ひとつの処方箋になりうるのではないだろうか。
「見る→過ごす」体験価値の転換
今回の万博のシンボルといえば、「大屋根リング」だろう。想像以上のスケールの大きさは圧巻で、上に「のぼる」という体験は強く印象に残る。

その大屋根リングで、来場者が何をしているかというと「歩く」だ。会場内を歩いて、リングに登って、また歩く。リングとはあくまでも眺めのいい長い道であり、どこか大きな見どころがあるわけでもない。


月の石に並ぶのでもなく、太陽の塔を見学するのでもなく、多くの人たちが2キロの道をただ歩く。そしてその体験を、SNSなどに投稿し、万博の象徴的な記憶と満足につながっている。
また、会場には地域の方のリピート来場も多く、「予約はしていないけれど、仕事終わりに立ち寄った」という人もいた。巨大な公園のような捉え方だが、そうした「ただ過ごす」がひとつの楽しみ方になっている。
さまざまなイベントやエンターテインメントであふれ、顧客体験や提供価値の向上に血眼になる中、逆に爽快だ。人とは、手取り足取り過保護にしなくても、勝手に過ごして、勝手に楽しむ力がある。もちろん素晴らしい場所があり、大量の費用と人員が投下されている上での場所だが、過ごし方という点で従来のイベントとの違いを感じた。
連日、現地やメディア、SNSで賑わいを見せる大阪・関西万博。
主語が大きくなるが、資本偏重主義に対する警鐘が鳴らされて久しいなか、それでも目に見える大きな変化はまだ少ない時代。社会の価値観がようやく次に移る、その境界線にあるのが、2025年の万博184日間という捉え方もできるのではないだろうか。
そのような変化の空気を現地で感じられたことが、何よりも大きな収穫だった。


Ambitionsでは、万博の「その後のパラダイム」に着目。
ビジネスリーダーへの取材を通して、これからの社会の姿を追う予定だ。
