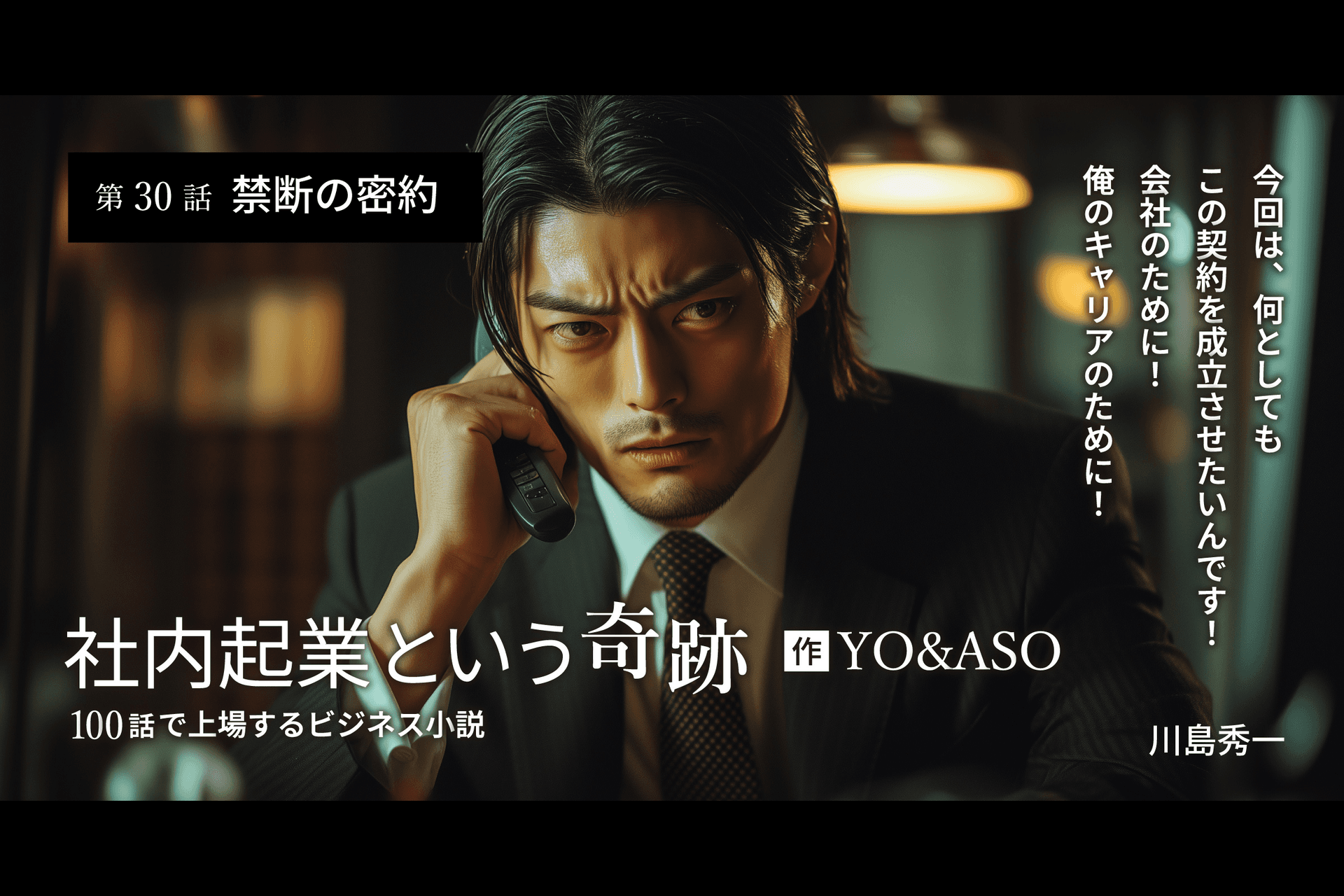
これは、スター社員でもなんでもない、普通のサラリーマンの身の上に起きた出来事。ひとりのビジネスパーソンの「人生を変えた」社内起業という奇跡の物語だ。
「頼む! 何とか、この契約だけは…」
夜遅く、人気のないオフィスビルの一室。川島は、電話口の相手に土下座するような勢いで頭を下げていた。彼の目の前には、契約書の山。それは、川島が社運をかけてまとめ上げようとしていた、新規の大型業務提携に関するものだった。相手は、次世代通信規格「6G」のインフラ開発で世界的に注目を集める巨大ベンチャー企業「グローバルコネクト」。この提携が実現すれば、富士山電機工業は電子部品供給の独占契約を獲得し、業界トップの座も狙えるほどの圧倒的な優位性を築けるはずだった。
しかし、その裏で川島は、会社も知らない危険な賭けに出ていた。グローバルコネクト側は、独占契約の条件として富士山電機工業の持つ特許技術のひとつを無償で提供することを要求してきたのだ。しかも、その技術は軍事転用可能な技術であり、国際的な規制の対象となる可能性もあった。

「川島さん、君もわかっているだろう。こんな強引な進め方で日本法人として契約をすることなんて、通常はあり得ないんだ。今回の件は異例中の異例だ。本来なら本社の承認はもちろん、総務省への届出も必要な案件なんだぞ。」
電話口の相手は、グローバルコネクトの日本法人代表・黒崎悠人だった。彼は、川島の焦燥をよそに、冷淡な口調で条件をのませようとしてくる。
「わかっています! しかし、今回は、何としてもこの契約を成立させたいんです! 会社のために! 俺のキャリアのために!」
川島は、歯を食いしばりながらそう言った。彼は、この大型契約を成功させることで、社内での地位を不動のものにしようと躍起になっていた。学生時代から常にトップを走り続け、輝かしい成果を手にしてきた川島にとって、出世は自らの価値を証明するための絶対的な指標だった。誰よりも早く部長になり、ゆくゆくは役員に名を連ねる。それは、彼にとってもはや執念と化していた。
一方で、彼の焦りは日増しに強くなっていた。同期入社組の中では川島の評価はトップクラスだったが、3つ上の先輩に鬼塚という男がいたのだ。鬼塚は営業部で圧倒的な数字を叩き出し、若くして重要なプロジェクトを任されるなど、まさにエリート街道を驀進していた。近年では、海外の大手企業との大型契約を成立させたことで社内での評価はうなぎ登り。一部では、次期役員昇格候補の筆頭としてその名が挙がっているという噂も耳にするようになっていた。
年次も考慮すると、このままでは鬼塚に大きく水をあけられることは明白だった。もしこのタイミングで鬼塚が役員に昇格すれば、出世レースにおいて決定的な差をつけられることになる。そうなれば、川島が将来的な社長レースの候補に名乗りを上げることは、極めて困難になるだろう。
川島は、一か八かの大勝負に出る必要性に迫られていた。
「いいだろう。今回だけは特別に、君の熱意を買って契約を承認しよう。そちらの社内承認も当局への届け出も、必ず追って調整してくれ。そして、我々のグローバル本社が、特許を何の分野でどう使おうが止めることは許さない。この件に関する情報は、すべて極秘扱いとすること。もし万が一にも、この件が外部に漏れたら。君も、私も、そして、両社にとっても。取り返しのつかないことになることを肝に銘じておくんだな。」
黒崎は、意味深な沈黙の後、川島に口止めを条件として契約を承諾した。それは、コンプライアンス違反はもちろんのこと、一歩間違えれば国際問題に発展しかねない、危険な密約だった。
「わ、わかりました。この件は、誰にも、口外しません。」
そして黒崎は重ねた。
「そしてそれに加えてもうひとつ。先日、富士山電機工業が起こした大規模なセキュリティ問題の件について、貴社の体制や考えをレポートにして報告してほしい。我々のグローバル本社は通信技術の会社だ。セキュリティ問題を起こすような提携先で大丈夫なのか、本社が慎重にやれというスタンスをとってきてる。それもあって、本来は性急に進めるのは難しいんだ。そのことをよく理解してほしい。」
「わかりました。先日のセキュリティ問題の件は追ってレポートを提出します。現在は万全の体制をとっており、もう二度と引き起こすことはありません。」
川島は、冷や汗でシャツを濡らしながら、力なくそう答えた。成功への執念が彼を底なしの闇へと引きずり込んでいく。そして、この時の川島は自らが手を染めた闇の深さが、やがて自分自身だけでなく、会社全体を揺るがす事態へと発展していくことを知る由もなかった。
その頃、増井たちは、五十嵐をチームに迎え、着実に開発を前に進めていた。
