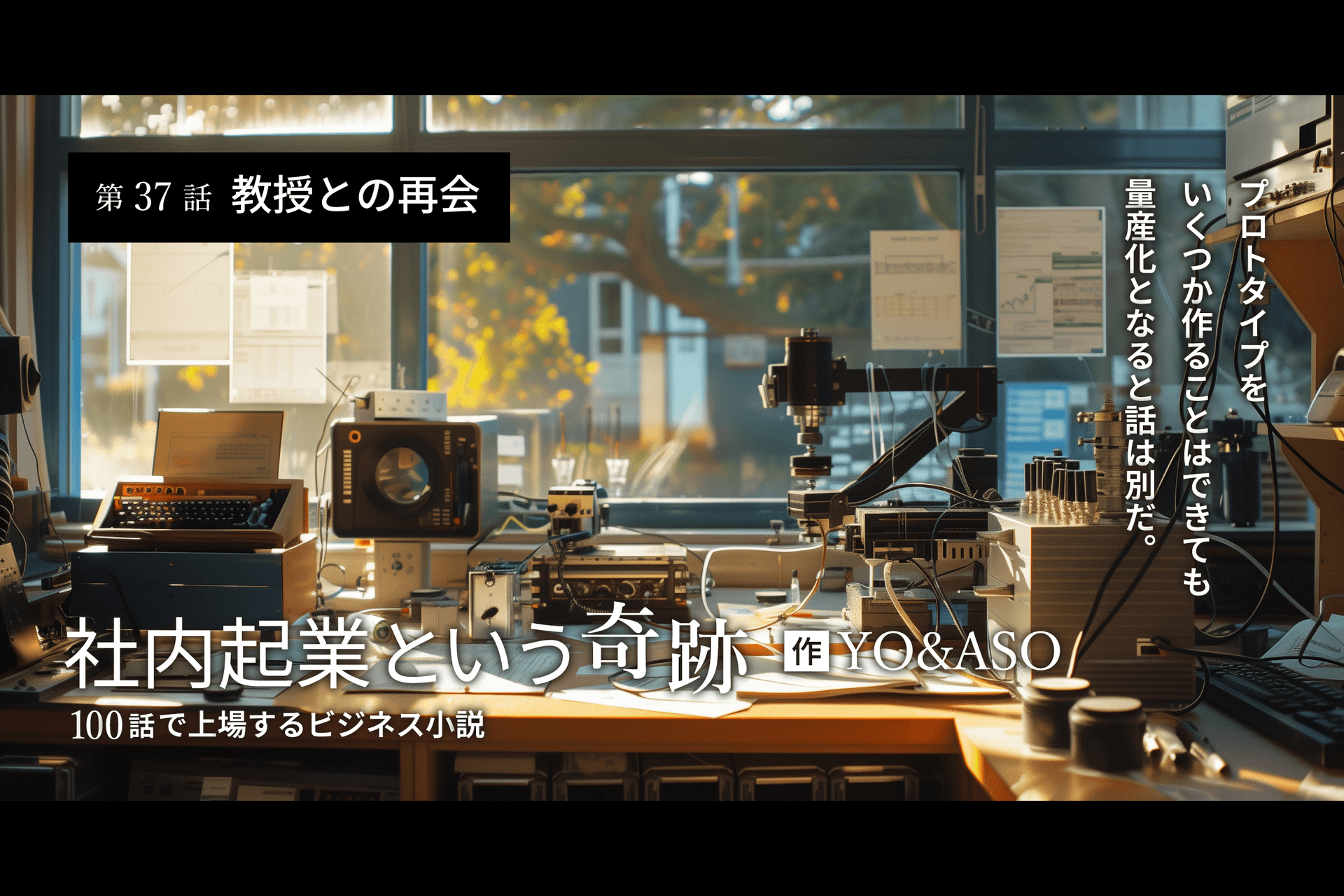
これは、スター社員でもなんでもない、普通のサラリーマンの身の上に起きた出来事。ひとりのビジネスパーソンの「人生を変えた」社内起業という奇跡の物語だ。
増井と有田は、大学の研究室を訪れていた。窓から差し込む午後の日差しが、実験機材や書類で雑然とした室内を照らし、どこか懐かしい雰囲気を醸し出していた。
「いやぁ、久しぶりだな、有田君!」
有田の目の前にいるのは、白髪混じりの髪をオールバックに撫で付け、白衣を羽織った恰幅の良い男性、松田直哉教授だった。彼は、有田が大学時代に師事していたロボット工学の権威だ。

アクチュエーターの小型化・動きの繊細化の課題に向けて、増井と五十嵐が必死に調査・議論を重ねた中でたどりついた一本の論文があった。それは、たった1ヶ月前に発表されたものでありながら、まさに今回必要とする技術に近しい内容が示されていた。そして偶然にも、その論文の執筆者は、有田が大学時代にゼミに参加していた教授だった。
「先生、お久しぶりです。お元気そうで何よりです。」
有田は、恩師との再会を喜びながら教授と握手を交わした。
「学生時代にほとんど勉強していなかった君が、まさかこんなプロジェクトを立ち上げていたとは、驚きだよ!」
大きな声で松田教授は言葉を重ねた。
「で、君たちが開発しているというピアノ演奏補助装置というのは、一体どんなものなんだね?」
増井は、持参した資料を広げながらプロジェクトの概要と現在抱えている課題について説明した。
「なるほど。指の動きをアシストするアクチュエーターか。確かにそれは難しい課題だな。ピアノ演奏に必要な繊細な力加減や滑らかな動きを再現するには、従来のアクチュエーターではサイズが大きすぎるか、精度の面で足りない。」
教授の言葉は、増井自身の懸念を裏付けるものだった。しかし、諦めることのできない有田は言った。
「先生、実は五十嵐さんの会社が開発した、高精度の指先センサーがあるんです。このセンサーと先生の開発されたアクチュエーターを組み合わせれば…」
「ほう、それは、興味深い! 五十嵐君というのはクロスロード・テクノロジーの五十嵐君のことか!五十嵐君とは、以前から共同研究の話が出ていたんだがなかなか実現しなくてね…」
五十嵐の名前を出すと、教授は前のめりに言葉を重ねた。
「実は、私の研究室では近年、人間の筋肉の動きを模倣した、まったく新しいタイプのアクチュエーターの開発に成功したんだ。従来のものよりも小型で軽量、そして高出力なのが特徴だ。その技術についての論文が先日ジャーナルに採択され、学会発表も終えたところなんだ。この理論でアクチュエーターを作れば、人間の筋肉のように、柔軟な動きが可能で繊細な力加減も制御できる。」
教授はそう言うと、実験室の奥から小さな箱を取り出した。中には、銀色に輝く細長い筒状の装置が入っていた。
「これが、その新型アクチュエーターのプロトタイプだ。」
教授は、自信に満ちた表情でそう言った。増井は、その言葉を聞いて希望に胸が膨らんだ。
「ありがとうございます、先生! これは素晴らしい。まさに私たちが求めていたものです!」

「そうだろう。しかし、ものごとはそんなに簡単じゃない。これを実用化するとすれば、まだまだ解決の糸口が見えない課題が残っているんだ」
教授は、少し残念そうにそう言った。
「課題、ですか…?」
増井は、教授の言葉に不安を覚えた。
「ああ。このアクチュエーターは、特殊な素材と高度な製造技術を必要とする。私の研究室レベルではプロトタイプをいくつか作ることはできても量産化となると話は別だ。コスト面でも品質面でも、クリアしなければならないハードルは高い。」
教授の言葉に、有田は言葉を返した。
「量産化、ですか。」
「ああ。君たちが目指すのは、西園寺先生一人を助けることではないだろう? もし本当に、この技術で世界を変えたいと思うのなら、多くの人々が手にできる価格で、安定した品質の製品を大量に供給できる体制を構築しなければならない。」
教授の言葉は、重く増井と有田の心に響いた。
「先生、その量産化のための技術というのは?」
有田は、藁にもすがる思いで教授に尋ねた。
「うーむ。それは、私もまだ答えを見つけられていないんだ。」
(量産化…新たな壁か…)
増井は、心の中でそう呟いた。希望の光が見えてきてはまたすぐに影を落とす。光を掴むためには、まだ、多くの困難を乗り越えなければならないのだ。
