
天神のビッグバンは2度目だった――。 約60年前、1度目のビッグバンが起きた天神周辺エリアは、経済成長と自然の美しさの両方を大切に独自の都市成長を遂げた。そして現在、2度目のビッグバンにより街は大きく変化しつつある。 国内外企業や外資系ホテルの誘致が進み、スタートアップやスモールビジネス、個人店などあらゆるプレーヤーが共存・”染み出し”ながら、福岡市を彩っている。 そんな福岡市の過去と現在、そして未来について、九州大学大学院とURBANIX株式会社で都市研究を続ける岩淵丈和氏が分析する。

岩淵丈和
URBANIX株式会社 代表取締役CEO
1996年、福岡県生まれ。URBANIX株式会社 代表取締役。国内外の都心再開発や地域再生、都市間連携のプロジェクトにおいて、定量・定性データを用いたリサーチやコンサルティング、プロデュース事業を展開。
“赤く染まっていく”1度目のビッグバン

さかのぼること1960〜1970年代。福岡・天神の昭和通りや明治通り周辺ではオフィスビルの老朽化に伴って次々と高層ビルが建設されることになる。現在ほどの高さはないものの、「福岡に“摩天楼”ができた」と言われるほど大きな注目を集めていた。つまり天神に1度目のビッグバンが起きたのだ。
当時から画一的な再開発とは一味違い、1980〜90年代になると高層ビルの周辺エリアにアクロス福岡やキャナルシティ博多など、個性的で街のシンボルとなる商業施設が誕生。建築家・藤森照信氏は、コンクリートの超高層ビル群で無機質に「脱色」されていく東京に対し、「福岡は赤く染まっていく」と表現した。

資本主義的な経済成長だけでなく、自然や環境、美しさを大切にした福岡市は実験的な取り組みに寛容で、天神を中心にアート作品を公開展示したアートプロジェクトを実施するなど、古くから街は自分たちの「表現の場」であった。特に天神の大型商業施設周辺に古着店やカフェ、スモールビジネスなどの個性的な小規模店舗が増え、路地がにぎわい始めたのもこの頃からだ。
当時、長崎から特急かもめに乗って天神を目指す“かもめ族”、熊本から特急つばめに乗って天神を訪れる“つばめ族”と呼ばれる他県の人たちが、再開発の進む天神に集まり、ショッピングや観光を楽しんでいたという。
経済と自然の調和がとれた美しい都市として発展した福岡市。2010年に就任した高島宗一郎市長は「寛容な実験都市」という街のDNAを引き継ぎ、挑戦者を支援すべく2012年にスタートアップ都市を宣言。起業家やスタートアップに対するさまざまな支援や制度が整うこととなる。
イノベーション地区として、FGNの立地は「正解」
福岡市がスタートアップの街として成長することができたのは、街の特性が大きく影響している。海外の研究者によると、イノベーションや新しい価値観が生まれやすいのは都心から徒歩圏の周辺エリアで、迷路性の高い路地が複数あり、商店が密集した「フリンジ」と言われる地域だという。
オフィスビルや商業施設が立ち並ぶ大通りから一本入った天神・大名地区は、まさにフリンジと呼ばれるエリアだ。
そんな大名地区に、旧大名小学校をリノベーションしたスタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next(以下、FGN)」が誕生。ビル群に囲まれた環境ではなく、路面店や路地の多い場所につくられたFGNは、おのずとスタートアップが集まる“開かれた拠点”として定着することになる。

イノベーションが生まれる地区は密集性やつながりによるネットワークが必要と言われるなか、まさに大名はフランクに人とつながれるカフェや、開かれた路地、密集した店舗などの要素が合わさっている。FGNの立地は海外の研究を見ても、インキュベーション施設の立地として適しているといえるだろう。
また、創業期にFGNへ入居したスタートアップは、支援を受けて成長した後も、FGNにアクセスしやすい大名周辺エリアに残るケースが多いことが調査の結果、明らかとなった。FGNの支援を受けて終わりではなく、その後も周辺に残り続けるのは、大名エリアがスタートアップに適した特性を有する地域であることを裏付けている。
大名から春吉、今泉、薬院へ。イノベーターの移動が始まる
2012年に「スタートアップ都市宣言」を行い、2014年には国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定された福岡市。これにより、スタートアップ支援や規制緩和が進み、企業誘致の環境が整備された。
2015年になると福岡市は都市再開発プロジェクト「天神ビッグバン」を発表。1960年代に建てられて老朽化が進むオフィスビルや商業施設を一新することが決まる。高機能で耐震性・快適性の高いオフィスや商業施設を整備し、若者やビジネスパーソン、観光客が集まるアジアの拠点都市を目指したのだ。
2025年5月現在で完成した主なプロジェクトは、最新のオフィスビル「天神ビジネスセンター」や、ザ・リッツ・カールトン福岡などが入居する「福岡大名ガーデンシティ」、旧福岡ビル・天神コア・天神ビブレの跡地に建設された大型複合施設「ワンビル(ONE FUKUOKA BLDG.)」などだ。国内外の企業誘致も進み、天神の街は新たな顔を見せ始めた。
海外企業が入居できる広いオフィスや富裕層向けのホテルがつくられたのは、福岡経済にとって大きなプラスであることは間違いない。一方、天神周辺部のフリンジのような大名エリアで活動していた個人店にとって、ポジティブな影響だけではないかもしれない。天神周辺エリアへの人の流れが増加して需要が増す一方で、賃料が高くなれば大名の周辺地域へ”染み出し”ていくような傾向はあるだろう。
実際、個人店やスモールビジネスは大名周辺の赤坂や今泉、春吉、薬院などに”染み出し”ている。路地が多く店舗の密集性が高いフリンジの要素を備えたこれらのエリアは、大名と同じようにスタートアップやクリエーターが集まってくる可能性もある。つまり、今後は天神周辺エリア一帯の広いエリアが個店を支える土壌としての機能を強めていくかもしれないのだ。
しかし、こうした広がりが全てプラスに作用するとは限らない。地価や賃料の上昇に伴って、既存の個人店が撤退を余儀なくされるケースも既に見られ始めている。また、話題性やトレンドに乗じた短期的な出店が増えることで、地域としての文化的な深みや連続性が失われる懸念もある。都市のフリンジが持つ多様性や創造性は、その曖昧さや余白によってこそ保たれている側面もあるため、過度な商業化がその魅力を損なう可能性があるのだ。
楽観視するだけでなく、変化のスピードと質のバランスを見極める冷静な視座が求められる局面に入っている。
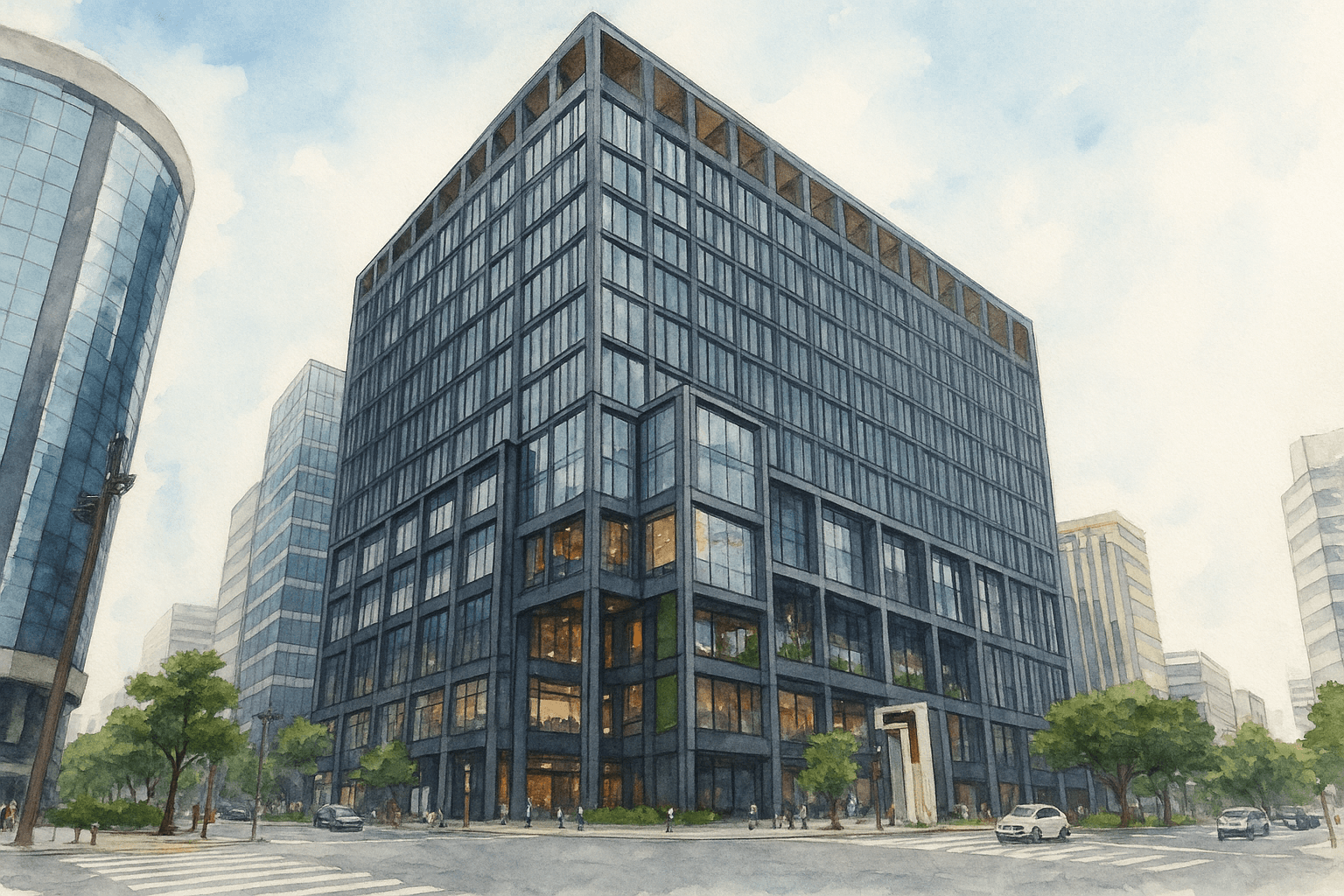
一極集中型からネットワーク型へ
福岡市の中心部以外ではどのような変化があったのか。大きな変化の一つとして挙げられるのが、1990年代から始まった九州大学の大規模な移転だろう。箱崎キャンパスと六本松キャンパスの機能は、福岡市と糸島市にまたがる広大な伊都キャンパスに移され、それぞれの跡地で再開発計画が進むことになる。
六本松エリアでは大型の複合商業施設がつくられ、その圧倒的な集客力を頼りに周辺には小さな個人店が次々と誕生。大名と違い、六本松エリアには「落ち着いた地域で自分らしく商売をしたい」「お客さんとゆっくりコミュニケーションを取りたい」と考える店舗が出店した。
この現実からいえるのは、今までは天神・博多一極集中的な都市成長だったのが、今後はそれぞれのエリアがそれぞれの個性で輝く“ネットワーク型”にシフトするのではないかということ。箱崎の再開発はこれからだが、箱崎らしい個性的な動きはたくさん出てくるはずだ。
また、個性的な地域は再開発によって生まれるとは限らない。博多駅から徒歩15分の場所にあり昭和情緒あふれる美野島エリアは、近年、若手クリエーターやアーティストがアートを通じて地域を盛り上げる取り組みが目立つ。商店街に大型アートスペースやアートギャラリーが誕生し、ワークショップも開催されるなど、下町情緒とクリエーターの感性が融合するユニークなエリアに変わりつつあるのだ。
実験都市として成長し、起業しやすい環境が整備された福岡市は、若者が自分のやりたいことに挑戦しやすく、自分の個性を表現しやすい街に成長している。都心部だけでなく、周辺エリアにも自分を表現できる場所はたくさんあり、特に若者世代にとってこれからの福岡市にはチャンスが多いといえる。
新しい取り組みやチャレンジに対して寛容性がある福岡市だからこそ、クリエイティブな挑戦ができる可能性がある。だからこそ今後は、単にチャンスの多さを語るだけでなく、そのチャンスが誰に開かれているのか、どうすれば多様な挑戦が共存できる都市であり続けられるのかを考えていく必要がある。
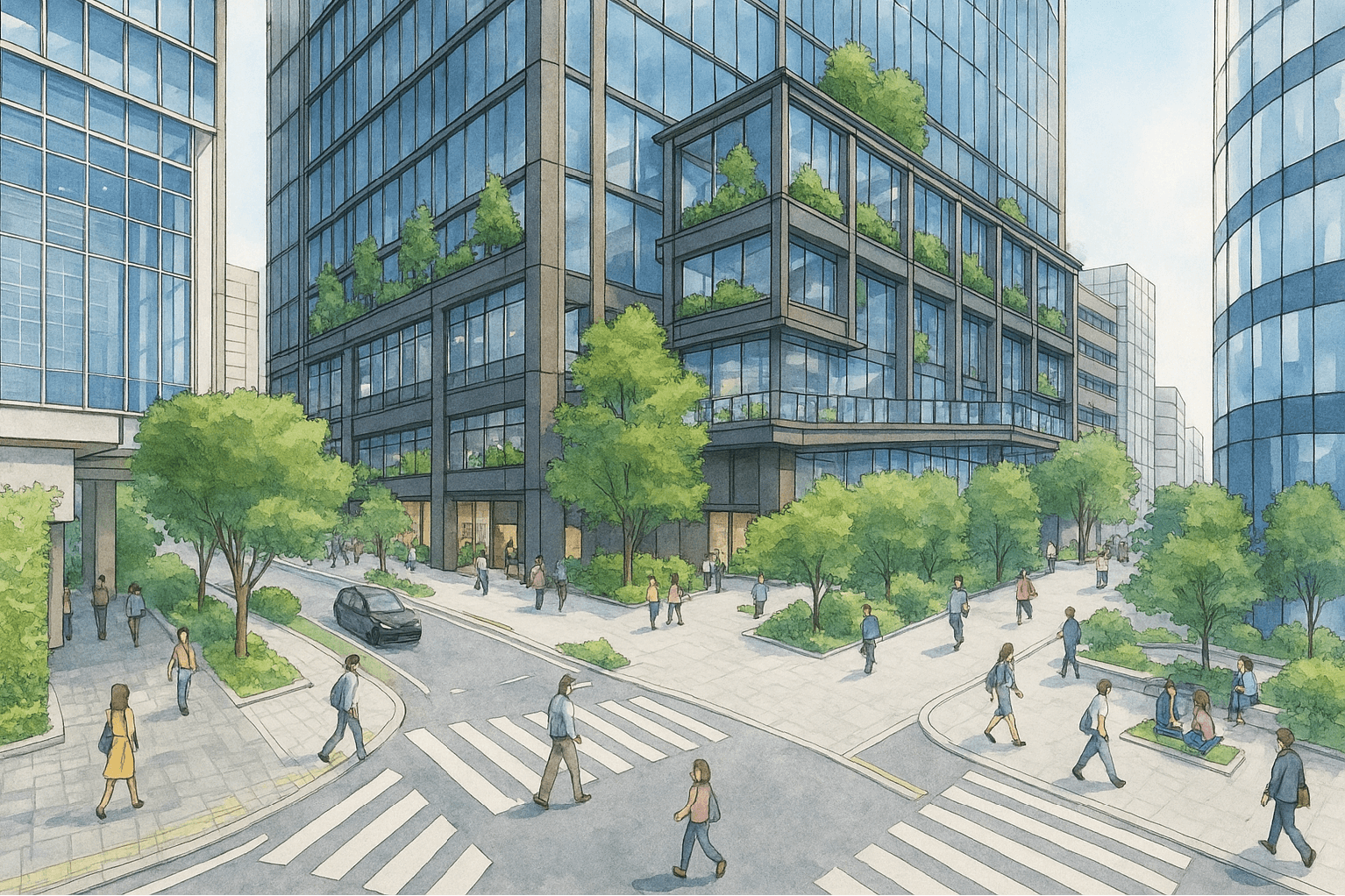
福岡市がクリエイティブシティとして成長する理由
アメリカの都市経済学者リチャード・フロリダは、都市が経済的・文化的に成長するには、人口や経済規模だけでなく「Talent(才能)、Technology(技術)、Tolerance(寛容性)」という3つの「T」が必要だと提唱している。
これを福岡市に当てはめると、福岡市はTalentとなる若者や移住者、大学などが多く、スタートアップや誘致企業などによるTechnologyの集積地でもあり、さらにクリエイティブやアーティストへのToleranceも兼ね備えている。つまり福岡市は、才能・技術・寛容性のすべてにポテンシャルが高く、クリエイティブシティとして成長し続ける素地があるのだ。
福岡市の先人たちは、代々街の寛容性を守りながら都市を成長させてきた。資本主義に翻弄されない余白が街にあるから、スタートアップやスモールビジネスが挑戦しやすく、若い人たちが自分の色を表現しやすい。これは、昔から受け継がれてきた街のDNAだといえるのだ。
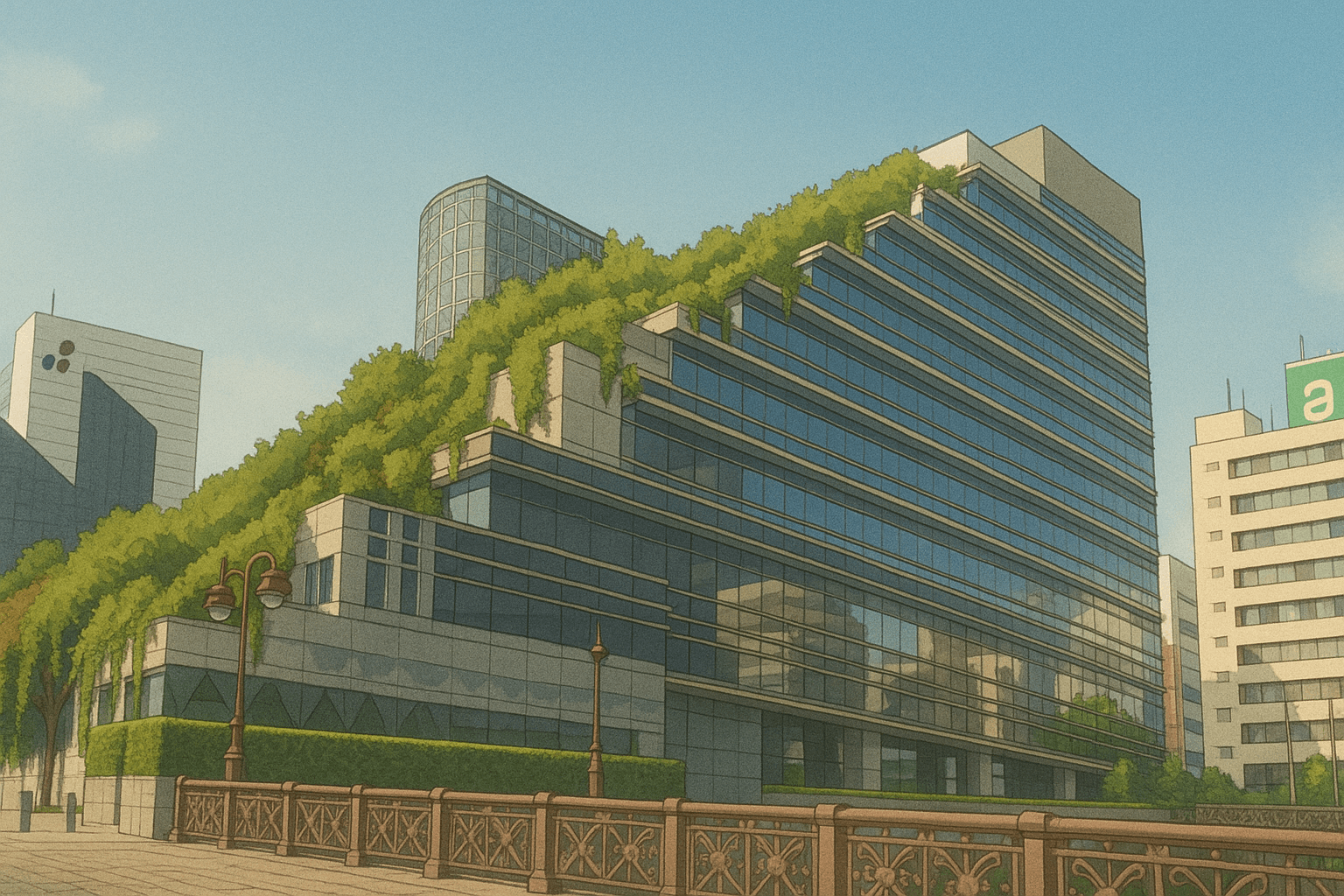
都市そのものが「表現の舞台」として成長し続けている福岡市。公園の再整備やビルの緑地化といったPark-PFI制度の活用も、都市に“余白”を残そうとする動きのひとつと捉えられる。
一方で、そうした整備が本来の自由度や多様性をどう変えていくのか、慎重に見極める視点も必要だ。グリーンやアートで都市を彩るDNAは受け継がれており、その延長線上で、どのような“余白”が生まれていくのかが問われている。
福岡市には有名なアーティストやクリエーターをはじめ、表現者になり得るタレントが豊富にいる。市内で生活する人はもちろん、国内外から福岡市で自分を表現したい人たちが集まるようになれば、想像もできない未来が待っているかもしれない。さまざまな制度や支援が整備され、美しい自然や環境、寛容性や余白を守り続けてくれた福岡市。これからは、若い世代が先人たちの思いに応え、ゼロイチで新しいものをつくっていく番ではないだろうか。
1960年代以降に「赤く染まる」と表現された状況は、これからきっと再び訪れる。かつて、高層ビルの周辺にシンボル的な存在としてキャナルシティ博多やアクロス福岡ができ、個性的な店舗が集まってきたように、天神ビッグバンをはじめとした再開発で建てられた高層ビルの周辺にも、これから新たなシンボルが求められる時代がやってくる。ただし、それを“ゼロイチ”でつくり出せるかどうかは、私たちの世代の意志と行動にかかっている。
各地で個性的なシンボルが生まれ、その魅力に呼応するかたちで、周辺エリアにユニークな店舗が集まってくる。1960年代以降に福岡市が歩んできた都市の変化と賑わいのプロセスは、いま、新たな時代感覚とともに“バージョンアップ”して繰り返されようとしている。
text & edit by Tomomi Tamura

Ambitions FUKUOKA Vol.3
「NEW BUSINESS, NEW FUKUOKA!」
福岡経済の今にフォーカスするビジネスマガジン『Ambitons FUKUOKA』第3弾。天神ビッグバンをはじめとする大規模な都市開発が、いよいよその全貌を見せ始めた2025年、福岡のビジネスシーンは社会実装の時代へと突入しています。特集では、新しい福岡ビジネスの顔となる、新時代のリーダーたち50名超のインタビューを掲載。 その他、ロバート秋山竜次、高島宗一郎 福岡市長、エッセイスト平野紗季子ら、ビジネス「以外」のイノベーターから学ぶブレイクスルーのヒント。西鉄グループの100年先を見据える都市開発&経営ビジョン。アジアへ活路を見出す地場企業の戦略。福岡を訪れた人なら一度は目にしたことのあるユニークな企業広告の裏側。 多様な切り口で2025年の福岡経済を掘り下げます。